|
■■■ ゲームレビュー ■■■
○ありそうでなかった?!卓球ゲームが登場!
さて、卓球というと一般的にどういうイメージがあるでしょうか?
おおむね二つに分けて、いわゆる温泉卓球的なレクリエーションとしての卓球と卓球少女愛ちゃんに代表される競技卓球に大きく分類されるとおもいます。残念ながらスポーツとしては、日本ではマイナーな扱いとなっている卓球ですが、上記のような温泉卓球文化は依然として存在していますし、別に温泉でなくとも、その辺のレクリエーション施設に行くと、なにはなくとも卓球台はかなりの確立でありますよね。そういった点においても卓球というスポーツの知名度は一般的に見ても高いといえるでしょう。
しかしながら、これだけ認知度の高い卓球ですが、不思議なことに卓球をあつかったゲームというのは非常に数が少なかったります。そんな状況で発売されたのが今回レビューを行う「Rockstar
Games presents Table Tennis(以下、Table Tennis)」となります。
なお、ゲームのジャンルとしては、超リアル路線の競技卓球となっています。
ちなみに、超リアル路線のゲームの場合、リアルすぎてゲーム性がなさ過ぎてしまい、「良く出来ているけどつまらない」ということが起きたりするのですが、今回の「Table
Tennis」はどのようなバランス取りがされているのでしょうか。
また、ジャンル的に近いゲームということもあるので、以前レビューをおこなった「トップスピン2」との簡単な比較も絡めつつ、レビューを行ってみたいと思います。
 
左はヒントの表示。通常、XBOX360のゲームの場合、ロード時間の最中の処理としてヒント表示を行うものがおおいが、TableTennisは非常にロード時間が短い為か、ヒントの表示はゲームの最中(自分が失点したタイミングなど)で割り込みの形で行われる。もちろんオプションの設定で非表示にすることも可能。右はリプレイの様子。いろいろな角度から表示されるので、かなり長く続いたラリーなどをリプレイで見れば、その緊迫感がある映像に、その内容が自分で遊んでいたものであるにも関わらずちょっとした驚きを感じるかもしれない。

○開発は以外にも、あの「GTA」を作成したRockstar Gamesが担当。もちろん日本語化もバッチリ。
Rockstar Gamesといえば、世界中で大ヒットし、日本語版も発売されたグランドセプトオート(GTA)シリーズを開発したことで有名なメーカーですね。ご存知の方も多いとおりGTAシリーズといえば、なんでもありのクライムアクションゲームの代表ともいわれるような内容であり、とてもではありませんが、同じメーカーから正統派の本格卓球ゲームが出てくるとは予想すら出来ませんでした。
もっとも、面白いゲームを作れるゲームメーカーというのは、何を作ってもしっかりと仕上げてくるものであり、今回の「Table Tennis」も非常に優れたゲームに仕上がっていると感じています。
なお、もともとは英語版のゲームとなりますが、しっかりとした日本語への対応が行われていますので、元が英語版であることを意識してしまうことはないですね。ゲームの作りとしてテキストの少ない内容ですので、必然的に言語に依存する部分が少ないのではありますが、それでも違和感なく日本語で遊べるという点は、やはり高く評価すべき部分だといえるでしょう。

○日本では知名度の高い卓球。なれど、ありそうなものの、実際にはあまりなかった卓球ゲーム。
前述のとおり、温泉卓球しかり卓球少女愛ちゃんしかりで、日本人で「卓球」というスポーツがあることを知らない人は殆どいないのではないでしょうか。それだけの知名度の高さを誇る卓球ですが、前述の通りゲームとしては殆ど扱われることのないジャンルでした。
以下はHP管理人の私見になりますが、例えば、テニスとゴルフと卓球を一度でも経験したことがある人という内容で統計を取ってみたら、おそらく卓球経験者の比率が一番高いのではないのでしょうか。それだけメジャーなスポーツですから、当然卓球ゲームのひとつやふたつはあってもなんら問題は無いと思うんですよね。実際にゴルフやテニスのゲームは非常に多く存在する訳ですし。
しかしながら、記憶を振り返ってみる限り、簡易な卓球ゲームはいくつかあったような気がするものの、本格的な卓球ゲームってあったっけ?というぐらい、印象が薄いのもまた事実です。これは、ゲームとしての面白さ云々というよりもは、ゲーム機側のハード的な限界が大きな障害になっているのではないでしょうか?
おおむね、いままであった卓球ゲームといえば、よくいえばアニメチック、悪く言えば簡易的なグラフィックが採用されていた印象があります。これは、テニスやゴルフと違い、ある程度違和感なくゲーム画面を構成する為には、そのほぼ画面全面にステージを表示する必要がありますが、卓球台とテニスコートとゴルフコースの大きさを比較をすると、必然的に卓球がステージの大きさは一番小さいため、相対的に一番人間を大きく表現する必要がでてきます。そして、大きなものを表示するというのは、結構マシンパワーが必要になります。
また、その大きく描かれた人物のコマ割が荒いと、これまたリアリティが極端に落ちるので、ある程度高速で人物の描画ができるマシンパワーが必要になります。
更に卓球の場合、卓球の玉の軌道が千差万別のため、昔の技法であるセル画的なグラフィックパターンを用意するのでは適切なラケットの軌道を表現するのには役不足となります。となると、リアリティ路線を捨てて簡易グラフィックにするか、最近の3Dゲームなどで採用されているゲーム内でリアルタイムによる人物描画を行う必要が出てきます。当然3Dでのキャラクタ表現に関しては、これまた多大なマシンパワーを必要とします。更に更に、打球に変化をつけるのが一般的な卓球では、その打球の動きにリアリティを追求すればするほど、精密な物理演算とその結果を的確に表現できる打球の緻密な表現力が必要となり、ここでも多大なマシンパワーを必要とします。
とまぁ、くどい位に「マシンパワー」という言葉を連呼してみたのですが、このように素人判断でちょっと考えただけでも「ちゃんとした卓球ゲームを作るのには、如何にマシンパワーが必要か」ということが容易に予想できます。これだけのマシンパワーは昔のゲーム機には当然ありませんでした。
そして、技術的な問題以外にも「卓球はスポーツとしてマイナーな為、ゲームも販売本数が稼げるかどうか微妙」という点も、ゲームを売るという営利活動においては、非常に大きな問題になることは火を見るよりも明らかですからね。そう考えてみると、今まで本格的な卓球ゲームがほとんどなかったことも納得できてしまう気がします。
もちろん、上記の内容はHP管理人の個人的な意見でしかすぎませんが、技術的な部分での推測を裏付ける、というほどの事実ではないのですが、実は「Table
Tennis」ではダブルスのプレイができず、シングルのみの扱いとなっています。これは、有り余るパワーを誇るXBOX360をプラットフォームにしているにもかかわらず、シングル(人間2体)の段階でその能力を使い切ってしまい、とてもとてもダブルス(人間4体)を表現するだけの余力がなかった為、との話を伝え聞いています。逆に言えば「Table
Tennis」が発売された2006年10月現在、最高の性能を誇るXBOX360の能力を使い切っているゲームであるという点においても、今現在で遊べる卓球ゲームとしては最高峰のリアリティを誇っているのが「Table
Tennis」の大きな特徴だといえるでしょう。
 
左は自分がサーブをする瞬間。よくゴルフゲームやテニスゲームなどで採用されているタイミング式がTableTennisでも採用されている。もっとも、タイミングはあまりシビアではないので、悪くても数回試せば確実に相手のエリアに打ち込めるようになる。右は、オプションの視点を変更し、遠距離モードに切り替えたところ。臨場感と見渡し範囲のトレードオフになるので、どちらで遊ぶかはお好みでどうぞ。

○実名プレイヤーは登場しないが、その人物描画は素晴らしいの一言。
先日発売されたテニスゲームの「トップピン2」では総勢24名の実名トッププレイヤーが登場しましたが、Table Tennisでは実名プレイヤーは一切登場しません。また、オリジナルキャラのエディット機能もありません。
その代わり、という訳ではありませんが、ゲーム内に登場するキャラクターの動作は、アメリカの卓球選手であるWALLY GREEN氏をはじめとする実際の卓球選手により、モーションキャプチャーが撮られています。
そのため、ゲーム内のキャラクタの動作に無理や無駄がなく、その部分でも高いリアリティを感じさせてくれます。
また、キャラクタのそのものの描きこみもハンパではなく、プレイ中に徐々に汗がでてき体の表面がライトに反射して光るなどの演出などを含めると、ぱっと見ではゲームか現実か一瞬自分の目を疑うこともあるぐらいのリアリティの高さを誇っています。個人的には、一般的な3Dキャラクタではどうしても違和感のある衣服の表現に関して、その自然さに驚きを感じましたね。
なお、ゲーム中に「KUMI」という日本人らしき人物が登場しますが、日本人であるHP管理人から見ると、どう見ても中国人か韓国人といった大陸系の人にしか見えません。まぁ、欧米人から見れば、日本人も中国人も韓国人も皆同じような感じに見えてしまうのでしょう。このあたりはどうしても人種の違いによる感受性の違いが出てしまう部分ですので、目くじらを立てるような部分でもありませんしね。ただ、実際問題として実在の人物をモデルを採用してしまうと、やはり似ていないという評価になってしまう可能性も十分にありますし、肖像権絡みで余計?な費用も発生しますので、いろいろな意味において「Table
Tennis」では実在の人物を扱っていないのも、またひとつの選択肢として正しいものだと考えています。

○基本操作はシンプルで簡単。それでいて多彩なショットが楽しめる。
ゲーム的に見ると、キャラクタの後ろに視点があるタイプが基本になり、そのほかにもう少し視点を上げて全体を見やすくするためのモードも選択できます。基本操作は非常にシンプルで、左アナログスティックで移動とボールコントロールを兼用。4つあるボタンで、ボールへのスピンのかけ方を使い分けるのが基本操作になります。そのほかにも出来る事はあるのですが、まずはアナログスティックでのボタンコントロールと4つボタンでの打球の質の使い分けだけを理解してしまえば、それでもう十分以上に「TableTennis」の世界を楽しむことが可能です。さらに突き詰めて言えば、ボタン4つなどと言わずに、アナログスティックとÅボタンだけでも十分にゲームを楽しむことが出来ます。その簡単な操作性は、プレイヤー側に超絶テクニックを要求することがなく、簡単操作で快適なゲームプレイを実現しています。そのため、まずはこのAボタンだけの超基本操作で操作感覚を覚えていき、徐々に操作方法を習得していく、というやり方がいいのではないでしょうか。このあたりは、「トップスピン2」と同じような感じですね。
この操作の手軽さによって、世代を問わず誰でも手軽に遊ぶことが可能となっています。この部分は大変高く評価ができる部分ですね。
 
左はコントロールの説明画面。もっとも、TableTennisは非常にシンプルな操作形態の為、なんとなく遊んでいても何とかなってしまう懐の広さがあるが、それでも操作方法がゲーム内で呼び出せるのは地味に便利。こういった細かい配慮がしっかりと実装されているのは好印象。右は見ての通りのガッツポーズ。オフラインでの対戦の場合、画面の中だけではなく、おもわずプレイヤーの方もガッツポーズを決めてしまうシーンも多いのではないだろうか?その熱中度の高さも、シンプルな操作性ゆえの賜物であろう。

○地味だが非常に作りこんであるグラフィックと、ゲームを盛り上げる気の効いた演出。
一言で言ってしまえば、グラフィックには派手さはありませんが、非常に良くできていますね。
細かい部分で作成側のこだわりが随所に感じられ、ボケーっと画面を見てる限り、もはや実写でしょ?といえるレベルまで到達していると感じています。もともと個人的には、あまりグラフィックにはこだわる方ではないのですが、3Dキャラクタの宿命ともいえる、テクスチャーの破綻(衣服を突き破って体が出てしまう等の現象)には終始気が付くことはありませんでした。ちなみに、エフェクトらしいエフェクトといえば、打球の質によって玉の周りに色付きのエフェクトが軽く掛かっている程度のものであり、それ以外の部分は、実際に卓球とほぼ同じで、卓球台と人物がメインとなり、あとは照明を落とした設定にして背景を殆ど描画していないというシンプルな画面構成ですので、どうしても画面から感じるイメージは、地味一辺倒です。まぁ、卓球そのものが地味なイメージが付いて回るスポーツですので、いい意味でも悪い意味でも、リアルすぎて地味、ということでしょうか。こう画面が地味だと、実際の卓球と同じようにシーンとしたステージで淡々と打球の音が響くだけのゲームを想像してしまいがちですが、実際のところ、テンションの高いBGMなどは流れてはいません。乾いた打球音が心地よく響いているだけ、という極めて地味な状態となっています。えぇ、本当にいたって地味です。もっとも、BGMは全くない、というのではなく、ある程度ラリーが続くと徐々にBGMが流れ始めプレイヤーのテンションを上げてくれます。その状態で更にラリーを続けると、画面の周辺部分がボヤーっとぼやけ、選手の集中力を視覚演出する仕組みが採用されています。どうしてもリアルに作れば作るほど地味になりがちな卓球というジャンルのゲームのゲーム性を上げる為に、こういった細かい演出にも配慮しているのが、Table
Tennisの評価を高くしている点だと思いますね。

○キャラクタ毎のパラメータシステムでキャラクタの特徴を表現化。
前述の通り、プレイヤー操作として超絶テクニックが必要ない、となると、ゲームとして各キャラの強さ弱さはどう表現しているかといえば「各キャラクターの能力は、パラメータ制」となっています。
各選手には、それぞれ特徴的なパラメータ割り振りがされているので、ゲームで遊ぶほうにしてみれば、操作レベルで超絶テクニックを駆使しなくても、選択した選手が強ければ操作レベルがそれなりの腕でも、トッププレイヤー並みの爽快感で遊ぶことができます。
これは、以前レビューをおこなったトップスピン2にも当てはまる点であり、この方向性がゲームとしての楽しむ為の方法論として正しい面が大きいことを示しているのだと感じています。
 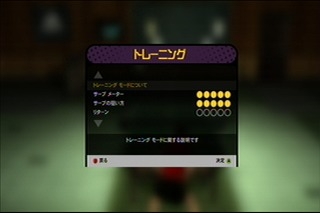
左が、対戦前に表示されるキャラクタの特徴をグラフで表現している画面。正直、あまり気にしても仕方がないので、まぁそんなもんか程度で認識していればOKかと。右はトレーニングモードでのメニューの一部。トレーニング内容は結構豊富だが、トップスピン2などと大きく違う点は、トレーニングをしたからといって、キャラクタの性能が上がる訳ではないということ。あくまでも人間が操作に慣れるためのモードのため、最初の方に遊んだら、あとは使うことのないモードかと。

○ボリュームは少なめ。長時間やりこむのではなく、思い出した時に手軽に遊ぶのにいい感じ。
Table Tennisはあまりボリュームがあるゲームではありません。簡単に紹介すると、以下の通りとなります。
・CPU戦を楽しみ、ゲーム内のいろいろなものをアンロックするためのトーナメント。
・オフラインでの対人戦やCPUとのフリー対戦を楽しむためのマッチプレイ。
・多種多様の操作をマスターする為のトレーニング。
・オンライン対戦を楽しむためのXBOXLIVE。
上記の通り、モードそのものはそれなりの数があるのですが、各モードとも、特段ボリュームが大きいものはなく、全体的なバランスとしては、一日何時間も遊んで、何ヶ月も骨までしゃぶるまで遊び尽くす、という感じではありません。どちらかといえば、ちょっとした空き時間にあそんだり、友達や家族との一時を演出するための小道具としてのゲームという位置づけになるのではないでしょうか?
実際、オフライン対戦では相手のリアクションが見えることや、その簡単な操作性で普段ゲームをぜんぜんやらない人でも、ものの10分もあればそれなりに遊べるレベルになります。対戦時間も短めな為、テンポも良いですので、パーティゲームとしての評価も大変高いと捉えています。正直、もしコントローラを一つしか持っていないのであれば、これを機に追加でコントローラを購入してでも、オフラインでの対戦を楽しんで欲しいものです。
 
左はメインメニュー。一見すると沢山のモードがあるように見えるが、ひとつひとつのボリュームはそんなに大きいほうではない。右はトーナメントモードの対戦表。自分が黄色の丸で表現されている。これは結構小さ目の大会の時の状況で、もっと大きな対戦ツリーになる場合もある。このトーナメントで勝ち進むことにより、使えるキャラクタや装備できる衣服パターンなどがアンロックされていく仕様の為、ある程度のやりこみ要素はある。

○良いことばかりじゃレビューにならない。
1.対戦プレイに比べると、イマイチ盛り上がりに欠ける一人プレイ。
対戦プレイでは、大変盛り上がる要素を秘めている「Table Tennis」ですが、CPUを相手にした、いわゆる一人プレイではイマイチ盛り上がりに欠けているような印象を受けますね。もちろんCPU戦がつまらない、というのではなく、対人プレイが面白すぎるので、それに比較してしまうとどうしても対CPU戦は面白さにかけてしまうような印象が残るんですね。
それとは別に、時々CPU側が人間離れしたスーパーテクニックというか、人としてその挙動はありえんだろ?という感じの動きをみせることがあります。これはどんなスポーツゲームにでもついて回る問題なのですが、「Table
Tennis」の様にリアルに人物を表現していると、その没入度はかなりのものになるですが、そんな状況の中で突然人物の挙動だけが人間離れしてしまうと、その部分にかなりの違和感を感じてしまいます。どうもCPU側にインチキをされているような印象をうけてしまって、一気に気持ちが褪めてしまうときが在ります。
このあたりの調整具合は本当に難しいところですし、また「人間離れ」という感じ方の線引きにも個人差がある為、誰にでも当てはまる感想ではないかとおもいますが・・・・。
2.スローモーションの演出は、果たして本当に必要なのか?
ゲーム内の演出効果のひとつとして、重要なシーンが一時的にスローモーションになるものがあります。これにより、選手の集中力の演出をしつつ、プレイの難易度も落とすことができるという目的をもった効果だとはおもうのですが、個人的にはこの効果は不要なのではないかと感じています。この効果があることにより、本格的に競技卓球の道を選んでいない大多数の人にとってはゲームでなければ絶対に体感できないような高速での打ち合いの気持ちよさが、かなり削がれてしまう印象を受けています。前述の通り、これがあると難易度が下がるのは間違いないので、一概に駄目機能と切り捨てることも難しいのですが、個人的には不要な演出だと感じています。

○総括
このゲームが発表された当時は「はぁ、卓球ですか・・・・」という印象しかなく、またリアルだけど地味なスクリーンショットをみてもあまり触手が動かなかった「Table
Tennis」ですが、それでもGTAを製作したRockstar Gamesが世に出した卓球ゲームということで少しだけ注目していたゲームだったりします。しかしながら、蓋をあけてみたらびっくり仰天。まさにゲームの王道を突き進む高いゲーム性をもつ内容に仕上がっていると感じています。こればっかりは、実際に遊んでみないと解からない部分ですね。いやはや、先入観とは恐ろしいもので。ただ、どこまでいっても限りなく地味な印象のある卓球というスポーツを主題にしたゲームをどう捉えるかは、やはり個人差と先入観によって大きく分かれる部分だとはおもいます。しかしながら、販売価格も4800円(税抜)とかなり低めに設定されていますので、ちょっとした合間に遊んだり、友人や家族と遊ぶための手軽なパーティゲームとして一家に一本あってもいいタイトルだとおもいます。
そして、対戦プレイとCPUプレイを比較すると、間違いなく対戦プレイの方が面白さを実感できますので、自宅に誰かを招いての対戦プレイが好きな方には、特に強くオススメできるゲームだといえます。是非多くの方に実際に遊んでもらってその面白さを体感して欲しいゲームだといえるでしょう。
|

